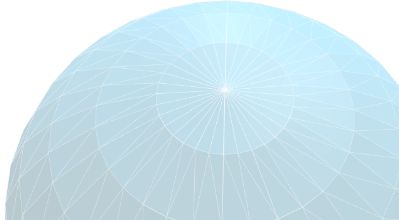「深山大沢」としての同志社

大学設立運動に奔走する晩年の新島襄にとって、「深山大沢」は大学の理想像でした。以下に「深山大沢」を含む新島の代表的な言葉を紹介します。いずれにおいても、新島の大学観や人間観(学生観)が明瞭に表れています。なお、新島晩年の愛唱句「深山大沢生龍蛇」は中国古典『春秋左氏伝』巻十六、襄公二十一年の一節「深山大沢、実生龍蛇」(「深山大沢、実に龍蛇を生ず」)に基づいています。右の画像は、徳富猪一郞(蘇峰)宛手紙(1889年11月9日)における新島の直筆です。
同志社は是非将来深山大沢になし度候間、貴兄も充分此之為に御工風御尽力被下度奉仰候
(「徳富猪一郞宛」手紙、1889年6月28日。『新島襄全集』4、165頁)
世人は我が同志社を評して只宗教主義の学校にして只伝道師を養成するのみと云う。夫れ或は然らん、如何となれば神学専門の一科をおきたればなり。吾人は此の一科を以て足れりとせず、此より進みて文学、法学、理学、医学等の諸学科をおき、宇宙の天理を講究し、社会の通則を学ばしめんと欲す。凡大学たるものは偏頗狭隘たるべからず、尤基礎を強固にし規模を寛大に為し、深山大沢龍蛇を生ずと申して之を深山大沢となし、器量の大、志操の高、目的の大なる人物を養成致し度きものなり。
(「大学設立主旨」、1889年8月16日、徳富蘇峰秘書写し。『新島襄全集』1、151頁)
願わくば、「深山大沢、龍蛇を生ず」の句を服膺し、当時〔現在〕学校に在るは、深山大沢に蟠るの感を持ち、将来、龍蛇となり、芙蓉峰〔富士山〕の上まで達せん事を期し賜え。
(「古賀鶴次郎宛」手紙、1889年11月2日。『新島襄の手紙』298頁。右図下図は新島が手紙に描いたもの)

学校も機械的の製造場に漸々流れ行くは、生徒の数も増したるより、自然の勢いにして、止む能わざるところもこれ有るべく候えども、小生平素の目的は、成るだけ法を三章に約し、我が校をして深山大沢のごとくになし、小魚も生長せしめ、大魚も自在に発育せしめ、小魚大魚、各おのおのその分に応じ、その身を世に犠牲となし、この美しき日本を早晩、改良して、主の御国、すなわち黄金時代に至らしめん事は、小生の日夜、熱祈して止まざるところなり。
(「横田安止宛」手紙、1889年12月30日。『新島襄の手紙』316頁)
「深山大沢」につながる新島襄の言葉
「深山大沢、龍蛇を生ず」において「龍蛇」は大人物を意味しますが、それは新島の遺言の一つ「同志社においては、倜戃不羈なる書生を圧束せず、努めてその本性に従い、これを順導し、もって天下の人物を養成すべき事」(1890年、『新島襄自伝』401頁)へと結実していきます。
他方、「我が校をして深山大沢のごとくになし、小魚も生長せしめ、大魚も自在に発育せしめ」は、同志社 創立10周年記念講演の際に、退学処分となった学生を想い、涙を流しながら語った「諸君よ、人一人は大切なり。人一人は大切なり」を強く連想させます。
そのほか、ネクスト「深山大沢」ミッションに関係する新島の言葉として以下のようなものを挙げることができます。
[宇宙観・自然観]
大学は智識の養成場なり、宇宙原理の講究所なり
(「私立大学設立の旨意、京都府民に告ぐ」、1888年。『新島襄教育宗教論集』54頁)
※上述の「大学設立主旨」においても「宇宙の天理を講究し」という大学がめざすべき方向が示されています。アーモスト大学で天文学を学んだこともある新島にとって、「宇宙」は探究すべき重要テーマでありました。
看山高巍々 観海闊洋々
味得造化妙 小心少発揚
山を看るに高くして巍々たり 海を観るに闊くして洋々たり
味わい得たり造化の妙 小心少しく発揚す
(「横田安止宛」手紙、1889年。『新島襄の手紙』319頁)
※山や海などの自然の壮大さに心躍らせながら、その背後にある神による創造の神秘を表現した漢詩です。新島においては、自然科学とキリスト教信仰は一体的なものとして理解されていました。
[教育観・共同体観]
小生畢生の目的は、自由教育、自治教会、両者併行、国家万歳、小生の心情、ご洞察下さるべく候。
(「横田安止宛」手紙、1889年。『新島襄の手紙』301頁)
※新島は「自由教育」を自らの人生の最大目的の一つに位置づけました。学び、真理を知ることによって、人間を不自由にしている心のあり方や社会構造を洞察し、その隷属状態から解放されていくことを新島は求めました。21世紀の「自由教育」は空間的・時間的制約からの「学び」の解放を促していると理解することもできます。また、同志社大学が目下進めている「アドバンスト・リベラルアーツ」は「自由教育」の理想を現代において実現しようとするものです。上述の「自治教会」は、具体的には会衆派教会のことですが、どのような権威からも自由な、新しい共同体の理念を示しています。
[人生観・良心観]
生のごときは日暮れて途(みち)遠く、なお克(よ)く駑馬(どば)千里を駆くる能(あた)わずといえども、ただただ我が良心を真理に照準して使用し、天より賦与するところの力を竭(つ)くして一生を終わらんと欲するのみ。
(「徳富猪一郎宛」手紙、1882年。『新島襄の手紙』167頁)
智識、財産、自由、良心の働きを養生する事。この内一も欠くべからざる事、恰も卓の四脚あるが如し。
(演説草稿「文明を組成するの四大元素」、1882年。『新島襄教育宗教論集』283頁)
※新島が米国で出会った英語のconscienceはギリシア思想に由来する長い系譜を有しており、西洋概念としての良心の語源的な意味は「共に知る」です。日本ではconscienceの訳語が孟子の「良心」から取られたため儒教的なニュアンスが今も強いですが、それに還元されない西洋史における良心の来歴を知っておくことは重要です。同時に、「次の環境」を考え、未来の世界を描くために、私たちは旧来の良心概念を拡張していく必要があります。ネクスト「深山大沢」では、未来世代と「共に知る」、大地と「共に知る」、人工物(AI・ロボット)と「共に知る」良心を展開していきます。